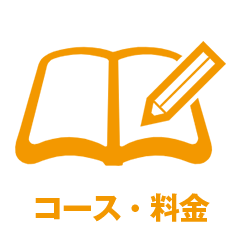学習習慣をつけることの重要性
2025.04.28ブログ

皆さん、こんにちは。
学び舎エルムの岩間です。
世の中的には、ゴールデンウィークが始まりましたね。
とある情報番組で、4割弱の方がお家で過ごすという調査結果が報道されておりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
ゆっくりお家で過ごす、旅行に出かける、などなど、素敵な休日をお過ごしください。
さて、今回は「学習習慣の重要性」について、僕なりの考えをお話しさせていただこうと思います。
保護者の方にも、これからお子さんの学びを支えていこうとしている方にも、何か参考になればうれしいです。
- 学びは「習慣」になったときに力を発揮する
日々、子どもたちと接する中で、僕が強く感じているのは、「勉強は才能よりも習慣だ」ということです。
特に小学校低学年、もっと言えば幼児期から、学ぶことを生活の一部にすることが、その後の学力形成にとって大きな土台になると考えております。
例えば、ある日常の一コマ。
学校から帰ってきて、遊びに行って、習い事に行って、ご飯を食べて、夜に「宿題やったの?」と親御さんに言われて、ようやく勉強を始める・・・。
こういった流れが、意外とあったり・・・。
でも、これでは、「勉強=後回し」「勉強=やらされるもの」という印象が強くなってしまい、学習習慣はなかなか身につきません。
- 「生活の導線」に勉強を組み込む
大事なのは、「帰ってきたら、まず宿題をやる」「その後に遊びに行く」といった、勉強が生活の流れの中に、自然に組み込まれることです。
まるで歯みがきのように、「やるのが当たり前」になっていくと、子どもたちは勉強を重たく感じなくなります。
エルムも、そうした生活の導線の中に位置づけられる場所になれたら、と日々考えています。
「帰ってきたら、エルムで宿題を終わらせる」「分からないところを先生に聞いてスッキリする」「そのあとに遊んだりゲームしたり」
そんなふうに、エルムが日常の一部になって、無理なく自然に学ぶ力を育てていけたら、嬉しい限りです。
- 知識の「芽」は日常の中に
また、生活に組み込むべきなのは、単なる「勉強時間」だけではありません。
勉強に関する「知識」も、生活に組み込んでいくことが大切です。
知識の芽は、日常の中にたくさん転がっています。
例えば、ケーキを切り分けるときに「これは8分の1ずつだね」と話したり、買い物のときに「50%オフって、いくらになるかな?」と一緒に考えたり。
そうした会話の中で、子どもたちは勉強の内容と日常生活のつながりを実感し、「学ぶって面白い」「こういうふうに使えるんだ」という気づきを得ることができます。
勉強が机の上だけのものにならず、生活とつながっていくこと。
これも学習習慣の大切な一側面です。
- 寄り添い、ともに歩む学びの時間を
エルムでは、塾生一人ひとりのペース、性格、生活に寄り添いながら、「一緒に考える」「一緒に学ぶ」時間を大切にしています。
習慣というのは、強制や根性ではなく、安心感と積み重ねの中で育っていくものだと思っています。
だからこそ、小さなころから、学ぶことを特別なことではなく、「日常の一部」にしてあげたい。
そのための伴奏者として、エルムが役に立てたら、こんなに嬉しいことはありません。
実は、エルムでは小さいころからの「学びの場」になれるよう、小学1年生~3年生対象の「低学年コース」を開講予定です。
詳細は5月頃、正式にお伝えできる見込みです。
準備が整いましたら、改めて当ホームページでお知らせいたします。